

公開日:2024.08.02
更新日:2025.03.29

製造業でよく使用されている作業指示書は、作業漏れや情報の伝達ミスを防ぐために欠かせないアイテムの1つ。正しく運用することで、作業の正確性や効率性は大幅にアップします。
そこで今回は、作業指示書の目的や記載すべき基本項目などを詳しくご紹介。すぐに活用できる作業指示書の無料テンプレートもプレゼントしていますので、生産性向上を目指す企業担当者さまは、ぜひお役立てください。
目次

作業指示書とは、特定の作業を実施する際に、作業内容・担当者・スケジュール・必要資材などを具体的に指示する文書です。「指示書」や「業務指示書」と呼ばれることもあり、製造業をはじめとするさまざまな業界で活用されます。
作業指示書と混同しやすいドキュメントとして作業標準書と作業手順書がありますが、具体的には下記のように異なります。
作業指示書は、現場の作業員が実際に業務を遂行するための「直接的な指示」を含む文書です。そのため、作業標準書や作業手順書のようなマニュアルとは目的が異なります。
また、作業指示書には「手順」だけでなく、作業に必要な情報が含まれます。むしろ手順の詳細については、作業標準書や作業手順書を参照したり、そこから必要な部分を抜粋して記載したりすることもあります。
関連記事:
>>作業手順書の作り方をチェック!製造業に必要な内容と効果的な運用ポイントを解説
作業指示書の作成自体は法律で義務付けられていません。しかし、業務の安全性や品質管理を明確にする文書として、作業標準書や作業手順書とともに多くの企業で活用されています。
関連する法的根拠として、以下のような法規があげられます。
・労働安全衛生法(労働安全衛生法第28条など)
労働者の安全を確保するために、作業手順の明確化が求められます。特に危険有害業務に関しては、作業手順の適正な指示が不可欠です。
・労働基準法(労働契約の明確化)
企業が従業員に指示を出す際、作業内容や指示系統を明確にすることが求められます。作業指示書は、このような指示系統の透明化にも寄与します。
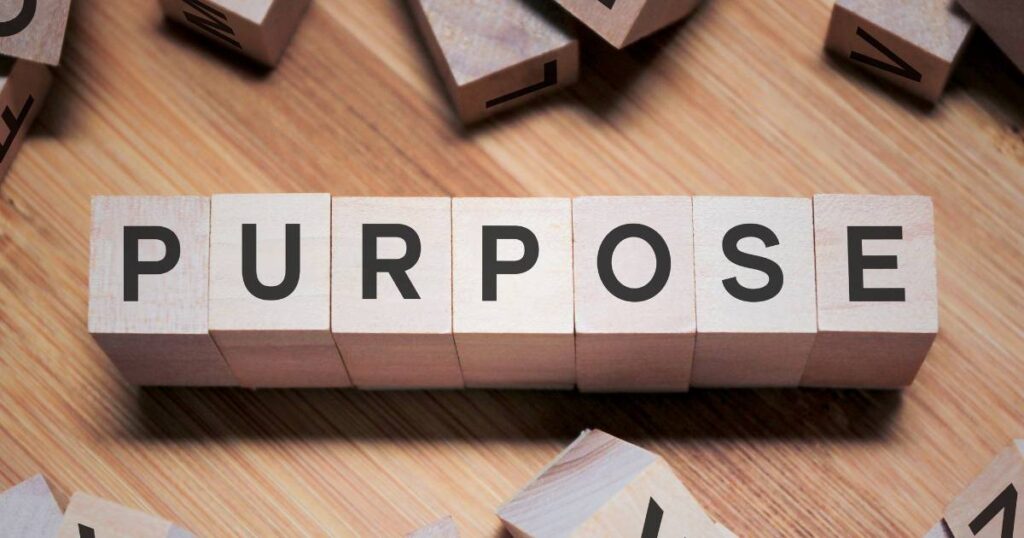
製造業で作業指示書を利用する目的は、主に3つです。
作業指示書には、作業内容が誰にでもわかるように記載されています。つまり、指示通りに作業すれば、ミスや納期遅れを防げるということ。
また、経験の浅い担当者が作業に取り組む場合でも、混乱を招くことなく業務を遂行しやすくなります。作業指示書は、作業を正確かつ効率良く進めるための重要な役割を担っているのです。
作業指示書は、教育にかかるコストの削減にも寄与します。手順や工程が複雑な作業を口頭で説明するには大幅な時間がかかりますが、作業指示書を使えば短時間で作業員に理解してもらいやすくなるからです。
作業の流れや注意点といった基本的な作業内容に対する理解が深まれば、教育コストを削減していくことができます。うまく運用できれば、業務と並行しながら個別指導やOJTをスムーズに実施できるようになるでしょう。結果として、新人作業員の即戦力化につなげられます。
製造現場では多くのケースにおいて複数の担当者が関わっていますが、作業内容を口頭で伝達しようとすると、伝言ゲームのように認識齟齬が起きやすくなります。
しかし、作業指示書を使えば、よりスムーズかつ正確な情報伝達・情報共有が可能です。作業指示書には進捗状況やトラブルの有無など、作業に関することが文章として正確に記録されています。作業員が交代したとしても記載内容を理解するだけで済むため、申し送りを人に伝えてもらう必要がありません。結果として、認識齟齬によるミスがなくなります。

作業指示書に記載する内容や書式に明確な決まりはありませんが、一般的には以下のような項目がよく盛り込まれています。重要な点は、書き手と読み手が共通で使用する言葉を用いることです。
作業名とは、作業につけるタイトルのこと。タイトルは、作業の取り違えを防ぐ目的を持つため、作業内容が具体的かつ簡潔に伝わるよう配慮することが重要です。見るだけで想起できる明確な作業名を記載できれば、作業指示書の保管や検索の際も無駄な手間を省けるようになります。
作業指示書には、作業の担当者・責任者の名前を書く必要があります。現場担当者の名前を記載しておけば誰宛ての文書なのかが明確になるため、責任の所在を明らかにできます。
また、作業責任者の名前を明示するのは、作業中に何らかのトラブルが発生した場合でも、スムーズに報告・連絡・相談できるようにするためです。担当者・責任者名と併せて電話番号やメールアドレスも記載しておくとよいでしょう。
問題が発生した場合の問い合わせ先として、機能する項目です。
また、作業の進捗や完了報告が必要なときにも利用します。担当者・責任者名と同様に、連絡先も明示しておくと便利です。なお、依頼者名を企業名にするのか個人名にするのかは、必要に応じて使い分けるとよいでしょう。
作業日・作業期間は、作業の遅延を防ぐ目的で記載します。「いつ作業するのか」「いつまでに何を終わらせるのか」を具体的に記載することがポイントです。作業にかかる時間やスケジュールが明示されていれば、作業者は時間配分を考えやすくなります。計画的に生産を進めるうえで、欠かせない項目です。
この項目には、作業の実施場所を記載します。作業員が現場を正確に把握し、速やかに作業に取りかかれるようにするためです。なお、作業場所が地図などで特定しにくい場合は、住所と併せてアクセス方法をわかりやすく記載しておくとよいでしょう。作業員が迷うことなく目的地に到着できるようになれば、作業遅延を防げます。
作業内容の項目には、作業手順や内容を詳細に記載します。「何をどうするか」「どのような作業をするか」という具合です。時系列に沿う・項目ごとに見出しをつける・箇条書きを活用する・図表を用いるなどの配慮があれば、よりわかりやすくなります。大切なのは、読み手がきちんと理解できるかどうかです。
また、場合によっては作業目的や作業人数、使用予定の工具・機器、作業時の注意事項などを記載したほうがよいケースもあります。実際に行う作業内容に合わせて、適宜工夫が必要です。
作業指示書の基本項目には含まれませんが、作業の進捗や結果を担当者本人が記録することで、実施内容と指示書との乖離を把握しやすくなります。「作業にどれくらいのリソースがかかったか」「予期せぬトラブルが発生したか」などの情報を残しておけば、次回以降の作業計画にも活かせるでしょう。
基本項目を網羅した作業指示書を一から作成するのは手間がかかるため、まずはテンプレートを活用するとよいでしょう。当社が提供している設備管理システム「MENTENA(メンテナ)」から出力し、編集したエクセルテンプレートを個人情報の入力なしでダウンロードいただけますのでぜひご活用ください。
ただし、これらの情報を紙やエクセルで管理・対応付けするのは難しいです。作業指示書と実績記録をスムーズに連携させるには、システムの導入を検討するのも1つの方法です。情報の一元管理ができれば、作業の属人化防止や運用効率の向上にもつながります。
関連記事:
>>不具合報告書とは?作成の目的・方法と記載項目を解説【テンプレート進呈!】
紙やエクセルで管理されることも多い作業指示書ですが、紛失や管理の煩雑さが課題になります。より効率的に運用するには、設備管理に特化したクラウドサービス「MENTENA」の導入がおすすめです。
MENTENAは、工場設備の点検や保全業務を効率化する設備管理システムです。クラウド上で作業指示書を管理できるため、以下のようなメリットがあります。
 従来の紙やエクセルによる管理では、作業ごとの進捗を一覧で把握するのが難しく、作業漏れや確認ミスが起きやすいという課題があります。
従来の紙やエクセルによる管理では、作業ごとの進捗を一覧で把握するのが難しく、作業漏れや確認ミスが起きやすいという課題があります。
MENTENAでは、各作業のステータスが色分けされて表示されるため、どの作業が完了していて、どれが未着手なのかが一目でわかります。
さらに、作業状況はカレンダー形式で視覚的に管理でき、設備ごとの作業計画/履歴とも連動しているため、誰が・いつ・何をするかが明確に可視化されます。結果として、現場の混乱やダブルブッキングを防ぎ、計画的な保全活動が可能になります。
 MENTENAでは、1つの変更がリアルタイムで全関係者に共有され、常に最新の情報に基づいた作業ができます。たとえば、急な設備変更や作業内容の修正があっても、担当者がそれぞれ別の資料を更新する必要はありません。
MENTENAでは、1つの変更がリアルタイムで全関係者に共有され、常に最新の情報に基づいた作業ができます。たとえば、急な設備変更や作業内容の修正があっても、担当者がそれぞれ別の資料を更新する必要はありません。
現場担当者、管理者、協力会社などが同じプラットフォームで情報を共有できるため、「言った・言わない」「古い情報を参照してしまった」といったトラブルを防げます。情報更新のたびに複数ファイルを修正する手間もなくなり、業務全体のスピードと正確性が向上します。

作業指示書や過去の履歴、設備図面などがバラバラに保存されていると、必要な情報を探すだけで時間がかかってしまいます。MENTENAでは、これらの情報がクラウド上で一元管理されており、作業担当者は必要なときにすぐアクセス可能です。
作業現場で「あの書類どこだっけ?」と探し回る無駄な時間が削減され、作業効率が大幅に向上します。
また、設備や作業単位で情報が整理されているため、新しい担当者でもスムーズに情報を理解しやすく、引き継ぎの負担も軽減されます。

文章だけでは伝わりづらい故障箇所や作業内容も、MENTENAでは写真や動画、音声メモを指示書に直接添付することができます。
例えば、「異音が発生している」「部品の一部が破損している」といった状況も、現場の映像や音声で共有することで、口頭や文章で説明するよりも正確に情報が伝わります。
これにより、管理者が現場に足を運ばなくても状況を把握でき、対応判断が早まり、的確な保全につながります。

「前回も同じような故障があったが、どう対応したのか思い出せない」といった場面でも、MENTENAなら過去の作業履歴を簡単に検索できます。
キーワードや設備名、作業日などでフィルタをかけて素早く類似事例を探し出せるため、前例をもとに最適な対処が可能です。
特にノウハウが属人化しがちな現場では、過去の情報を活用することで経験が共有され、ベテランに頼らずとも若手でも安心して作業を進められるようになります。
テンプレートでの運用を試したうえで、さらに効率化したくなったらMENTENAの出番です。
▶ぜひ、MENTENAの詳細資料をご覧ください。
作業指示書の運用で業務効率化や生産性向上を目指す場合は「漏れなく」「わかりやすく」「具体的に」記載することがポイントです。
また、MENTENAを活用することで、作業指示書の管理がスムーズになり、進捗管理・情報共有・過去履歴の検索が格段に楽になります。
MENTENAを導入する前に、まずは無料で使えるエクセルのテンプレートを活用し、作業指示書の整理・運用を始めてみるのもおすすめです。こちらのテンプレートは実際にMENTENA上から出力したエクセルファイルをもとに作成しています。ぜひご活用ください。
※テンプレートは個人情報の入力なしでダウンロードいただけます!
作業指示書に関心ある方へ、あわせて読みたい記事:
>>設備台帳はエクセルで十分?台帳作成のコツと効率的な管理方法を解説
>>エクセルで修理履歴管理を効率化!今日から始める無料ツールの運用方法
執筆者
MENTENA編集部
製造業向けの業務効率化・業務改善に役立つコラムやセミナー、および有益な資料を通じて、実践的な情報を提供しています。最新のツールの使い方や業界の情報・トレンドを継続的に発信することで、製造業の皆様にとって信頼できる情報源となることを目指しています。

© Copyright 2025 YACHIYO Solutions Co., Ltd.
All Rights Reserved.