

公開日:2024.06.25
更新日:2025.09.24
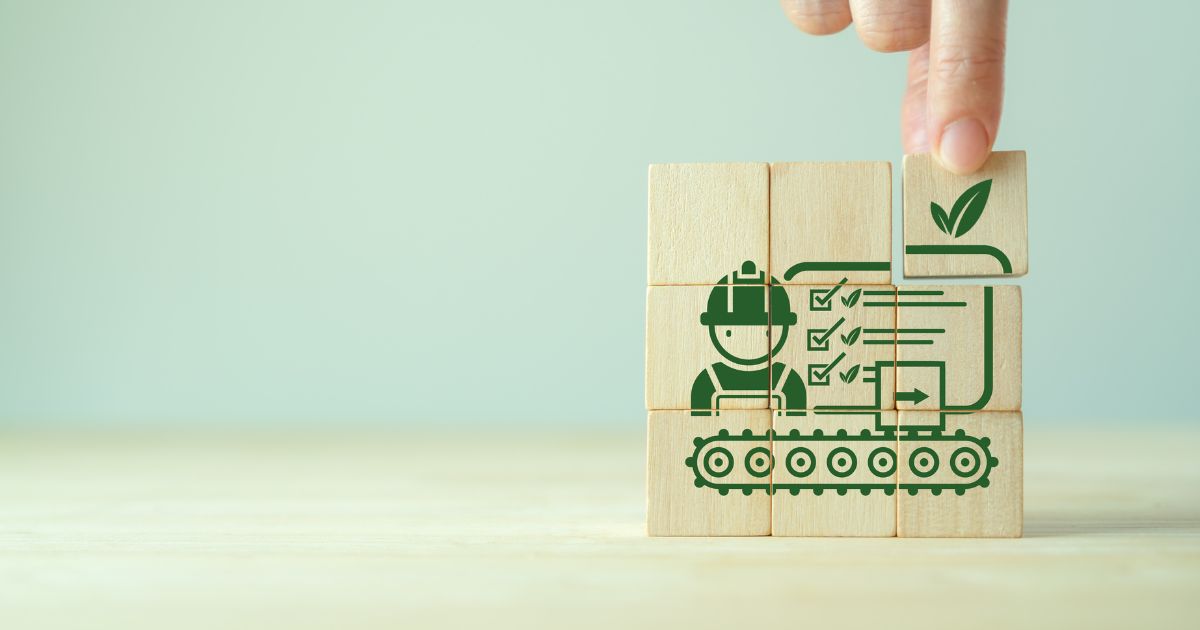
製造業の現場において、製品に必要な部品情報や構成情報をリスト化したBOM(部品表)は必要不可欠なアイテム。設計や購買、製造に至るまでの各部門で広く活用されるため、製造業に携わる方にとってBOMの作成・管理は身近な業務の1つでしょう。
これまでBOM管理の手法は紙やExcelもよく用いられていましたが、昨今ではシステム管理も注目されつつあります。本記事では、BOMの基本をおさらいしつつ、システム活用のメリットについて詳しく解説します。BOMの作成・管理による業務負担を改善したい経営者、管理者の方はぜひご一読ください。
目次
BOMとはBill Of Materialsの頭文字をとった略称で、日本語では部品表、部品構成表と訳されます。 BOMに登録されているのは、製品に必要なすべての部品の品名や型名といった詳細情報、部品構成など。そのため、製造の現場においては製品の基本情報として中心的な役割を担います。
BOMは設計部門や製造部門、購買部門と社内のさまざまな部門で活用されます。そのため製造業においては、部品調達のスケジューリングや工程管理、原価管理など幅広い場面で必要不可欠なアイテムといえるでしょう。
製造業の現場でBOMを活用する目的は、製品の生産管理を効率化し、製品の品質を高い水準で維持することにあります。BOMが現場でうまく機能していれば、製品を構成する各部品の手配状況や在庫状況などを正確に把握できるようになり、部品の手配ミスを未然に防げるようになるでしょう。
また、製品の設計変更などが生じた際には、型名の更新などによる部品の変更点を迅速に把握できるようになり、スムーズな対応が可能になります。その結果、効率的で正確な生産管理を実現でき、業務の質を向上することができるのです。
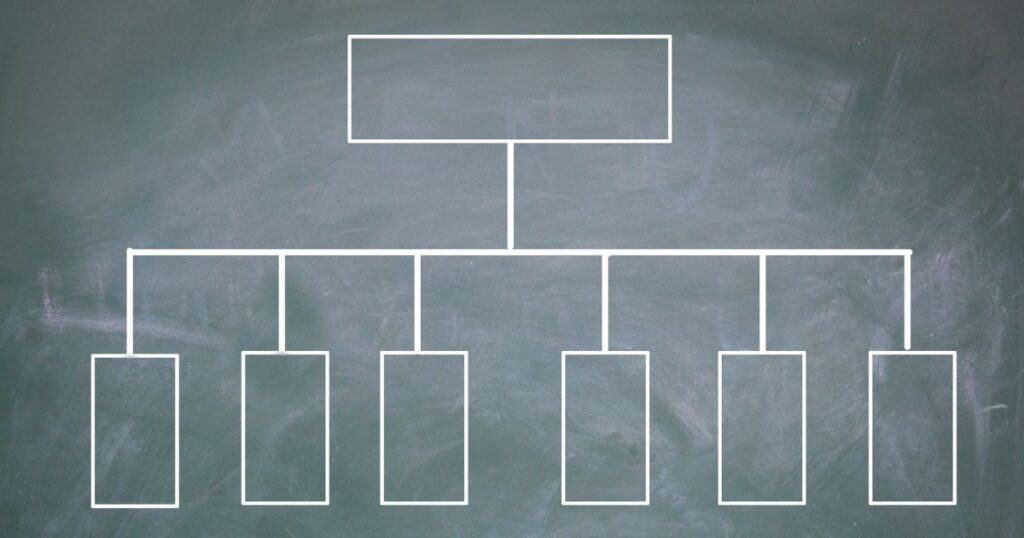
BOMの種類は、部品の管理方法と使用する部門の2つによって分類できます。
まずは、部品の管理方法による分類から見ていきましょう。部品の管理方法によるBOMは、サマリ型とストラクチャ型の2種類。場合によっては、これらの2つを組み合わせたハイブリッド型が採用されることもあります。
サマリ型は、製品の組み立てや加工の順序に関係なく、必要な部品や材料を並列に一覧化する方法です。 どの部品が、どのくらい必要なのか一目でわかるようになっているため、主に資材部門や調達部門で活用されています。
部品追加や仕様変更があった際にも迅速に対応できるというのが、サマリ型のメリット。そのため、試作品や個別受注品など、仕様変更が起こりやすい製品に向いている形式でもあります。
ストラクチャ型とは、製品の組み立て順をふまえ、部品の親子関係(親品目・子品目)を階層構造でまとめる形式です。 部品の親子関係とは、1つの大きな部品を“親品目”とした場合、それを構成する小さな部品を“子品目”とする考え方のことです。
ストラクチャ型で部品管理をすると、製品完成までの加工順とそれにかかる予定工数、リードタイムの計算がスムーズにできるようになります。
また、仕様変更が生じた際には、その影響範囲や原価計算がしやすいというメリットもあります。
BOMは、設計段階から製造段階へ引き継がれたり、購買部門では発注の際に使用されたりとさまざまな場面で活用されます。このようにBOMはそれぞれの部門ごとに存在し、作成・管理されるのが一般的です。
E-BOMは、製品の設計段階で作成される部品表で、設計図面をベースとして構成されます。〜そのため、CAD(製図システム)などのシステムと組み合わせて活用される場合がほとんどです。
E-BOMは設計チームや製造チームが製品仕様や製造プロセスを細かく把握できるように、各部品の仕様や設計情報、技術情報などをまとめたものであり、製品製造全体の基盤となります。
M-BOMは、製造工程に重点を置いた部品表で、製造に必要な部品や材料、加工手順が詳細に記載されています。
E-BOMの情報に、製造工程で必要な情報を追加して利用するのが一般的です。製造工程の円滑なスケジューリングや効率化、品質管理において重要な役割を担います。
S-BOM(Sell-BOM)は、販売支援情報を登録し、販売支援システムと連携する方法が一般的です。
製造の現場によってはS-BOMの内容を、M-BOMによって管理することもあります。必要不可欠ではないため、補助的な部品表として使用されることも多くあります。
P-BOMは、発注が必要な部品や材料をリスト化した部品表です。 必要な部品の数量や仕入れ先、手配までの納期といった情報で構成されており、発注や在庫管理をサポートする役割を担います。
P-BOMを活用すれば、部品や材料の調達の流れが最適化され、在庫の過不足も少なくなるでしょう。
Service-BOMは、製品の修理やメンテナンスに必要な部品をリスト化した部品表です。 定期メンテナンスや突然の修理に対応できるように、保守サービスに必要な部品やメンテナンス履歴を管理します。

近年ではBOM管理システムの活用も増えています。それぞれの管理方法について特徴とメリット・デメリットを見ていきましょう。
紙によるBOM管理は、長く採用されてきた手法です。デジタルな作業やITスキルを必要とせず、誰でも簡単にデータを扱える点がメリットといえるでしょう。一方で更新や修正、チームメンバー間での共有がしにくく、記入漏れや誤記などの人為的ミスも起こりやすいというデメリットがあります。
Excelは、さまざまな現場で活用されているデータ管理の定番ツールです。柔軟な編集が可能で、ある程度の操作スキルや知識を持つ人材が多いのも利点でしょう。そのためBOM管理の手段としても広く採用されてはいますが、一方で複数人での同時編集に向かないというデメリットも。
部門をまたいでのデータ管理が難しいため、一元管理はほぼ不可能といえます。そのため、大規模なプロジェクトではデータの不整合などが起こりやすく、現場に混乱が生じる可能性もあります。
紙やExcelによるBOM管理が抱えていた多くのデメリットを解消できるとして注目されているのが、BOM管理の専用システムやソフトを活用する方法です。
近年は、BOM管理をシステム化する企業も増えています。システムによるBOM管理であれば、大規模なプロジェクトであっても混乱を最小限に抑えてデータを管理することができ、チームメンバー間でのBOM情報の共有や閲覧も容易になるでしょう。しかし、紙やExcelによる管理よりもコストがかかるため、現場の課題感や予算を見ながら導入を進める必要があります。
なお、システムによるBOM管理には生産管理や購買管理などその他の管理システムと連携して提供されるものもあります。
BOM管理をシステム化するメリットについて、さらに詳しく解説します。
これまで部門ごとに乱立していた部品情報をなるべく一元的に管理できる点が、システムによるBOM管理の大きなメリットです。各部門から同じBOMの情報を同時に閲覧し、活用することが可能になるため、データの不整合や非効率な作業重複が起こりにくくなります。
また、情報共有にかかるタイムラグも解消されるため、チームメンバー全員が常に最新のデータを得ることが可能に。発注や在庫管理も精度が増し、在庫の過不足を最小限に防ぐことができるでしょう。このように、部品情報を一元管理できれば、部品管理にまつわる工数を削減し、業務効率を向上させることができるようになります。
システムによるBOM管理の導入によってデータの入力や更新が自動化されると、ミスの削減につながります。ミスは製品の品質低下や製造の遅延につながることもあるため、業務の自動化は全体的な質の向上や製品への信頼性アップ、製造時間の短縮にもつながるでしょう。
関連記事:
>>ヒューマンエラー対策10選!製造業の現場でよく起こるポカミスを防ぐには

さまざまなメリットのあるシステムによるBOM管理ですが、導入するにはいくつかの課題もあります。
BOM管理システム導入時によく見られる問題の1つが、品目コードの不一致です。これは、同じ部品であっても、部門ごとに異なる品目コードが割り当てられている状態のことです。このままシステム導入すれば、同じ部品が品目コードの違いから別々の部品として認識されてしまい、重複登録が発生することがあります。
このような状態に陥らないためにも、システムを導入する前に、部品と品目コードが1対1になるように、あるいは異なった品目名でも共通用語を含めた表現にするなど、全部門で規格を統一しておかなければなりません。
各部門で別々のBOMを作成・運用していた場合には、それらすべてのフォーマットを集約することが重要です。しかし、品目コードの不一致をはじめ、仕様の表記や書式の違いがある状態では、集約することはそう簡単ではないでしょう。
特に、E-BOMとM-BOMを整備するのはBOMの中でも特に活用されるものの、煩雑な作業になるといわれています。
システムによるBOM管理を導入するためには、現場関係者の理解を得ながら、データの整備が必要となるでしょう。通常業務に加えて、準備作業が発生することになるため、しっかりとBOMのシステム化の重要性を社内へ周知することが大切です。
ものづくりにおけるBOMは、多くの部門が作成し、管理する基本情報です。それゆえに、BOMを整えることは製造プロセス全体の効率化に影響し、大幅な業務改善につながるでしょう。近年では紙やExcelによる管理に課題を感じ、システム化する企業も少なくありません。
製造業において、設備管理は生産活動の安定稼働に欠かせません。設備が故障すると、製造ラインが停止し、生産遅延や顧客への信頼低下を招きます。故障の原因特定に時間がかかったり、修理部品・代替え部品の納期が伸びたりすることによる、さらなるコスト増も考慮すべき重要な視点の1つです。定期点検と予防保全を行うことで、突発的な故障を最小化し、効率的な生産体制を維持できます。
当社の「MENTENA(メンテナ)」は、ものづくりの設備管理に必要な設備台帳や修理履歴、予備品管理などの保全情報の一元管理ができるクラウドサービスです。BOMの情報もPDFなどで合わせて保存しておくことで、突発的な工場停止の時間を圧縮する一助ともなりえます。保全情報の一元管理に課題感をお持ちの企業さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
執筆者
MENTENA編集部
製造業向けの業務効率化・業務改善に役立つコラムやセミナー、および有益な資料を通じて、実践的な情報を提供しています。最新のツールの使い方や業界の情報・トレンドを継続的に発信することで、製造業の皆様にとって信頼できる情報源となることを目指しています。

© Copyright 2025 YACHIYO Solutions Co., Ltd.
All Rights Reserved.